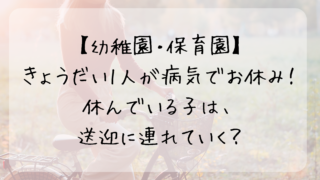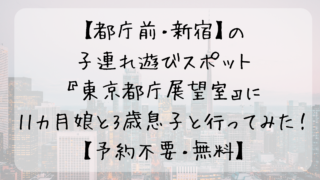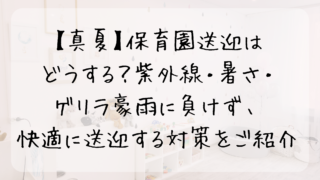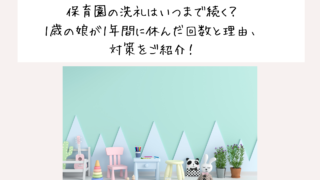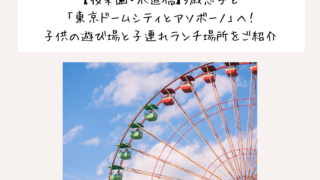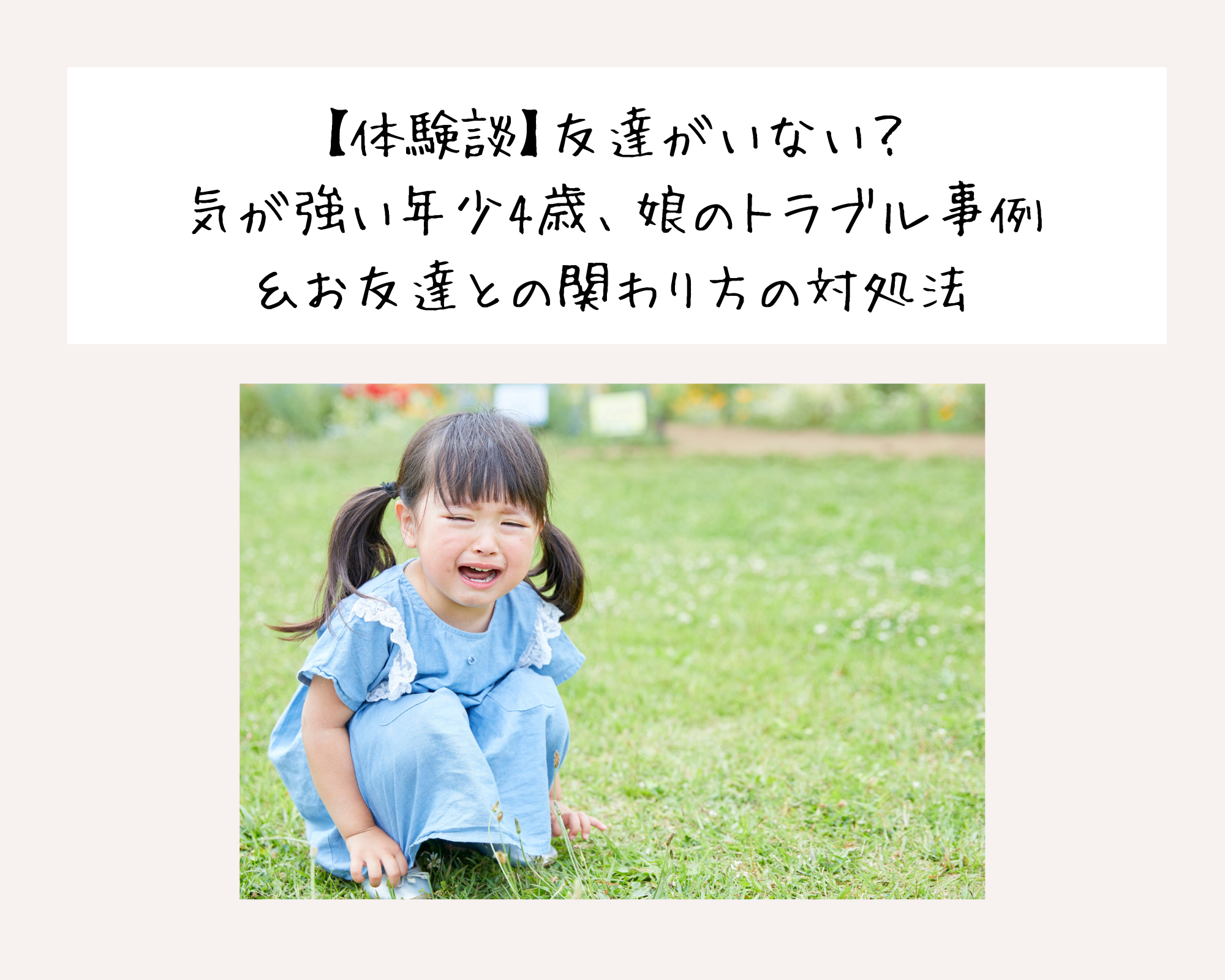年少になると、お友達と一緒に遊びたいという気持ちが少しずつ増えてきますよね。とはいえ、年少さんはまだ自分の気持ちを上手に言葉で表現したり、お友達の気持ちを考えながら遊ぶのは難しい年齢。それゆえ、お友達とのトラブルが発生してしまい、友達の輪に入れなくなってしまうことも。
今回は、一年生の息子の子育て経験があり、現在は年少4歳の娘の育児中である筆者が、体験談を元に年少のお友達トラブル事例とお友達との関わり方の対処法をご紹介します。
年少娘は気が強くてセンシティブ

我が家の年少の娘は、気が強い性格です。主張がハッキリしているため、遊びたい友達を独り占めをしたり、娘のやりたいことをするためにお友達が傷ついてしまう言葉を発したりしてしまうことがあります。
反対に、お友達の輪に入れてもらえなかったり、自分の思い通りにいかないことがあった翌日の朝は、泣いて登園渋りをすることもあります。
娘から保育園であった出来事を聞いていると、娘の気が強いことで、お友達が悲しい思いをしたり、困っていたりする面が大きいのではないかと思うこともしばしば。
しかし、自分の意思を伝え、やりたいことを実行できる力は悪いことばかりではありません。そのため筆者は、娘の良さでもある気の強さを無くすのではなく、お友達と上手に関わるにはどうしたら良いのか悩む日々を過ごしています。
保育園の年少クラス!娘のトラブル事例

画像:AC
我が家の小学校一年生の息子は昔からほとんどお友達トラブルがない子どもでした。鬼ごっこやサッカーなど体力を使う遊びが好きで、息子の遊びについていくのが大変でした。
しかし年少の娘は、お友達関係のトラブルなど精神面でのトラブルにヤキモキすることが多いです。
そこで実際に起きた、娘のお友達トラブルとやって良かった対処法をご紹介します。
- 女の子たちの仲間に入れない
- 好きな友達を独り占めする
- お気に入りの遊具を自分のものにする
- 強い口調や言葉で話す
女の子たちの仲間に入れない
我が家の娘は保育園に通っています。年少クラスの一学年下の2歳児クラスの時、娘がお友達に「いーれて」と言ったけれど、「お友達から「ダメ」と言われて一緒に遊んでもらえない」と毎日悲しい思いをしながら登園していました。
今もこの時の仲間に入れてもらえなかった経験がトラウマのようになっていて、一緒に遊びたいなと思う新しい友達がいても自分からは「一緒に遊ぼう」と言えなくなってしまいました。
最近では娘も、お友達から一緒に遊ぼうと言ってもらうと「ダメ!」と言うようになってします。
保育園のクラス担任にも娘がお友達に意地悪しているのではないかと相談しましたが、クラス担任からは「一人ひとりの気持ちを尊重することを大切にしている」といった回答で、お友達みんなで遊べるようには取り持ってくれないようでした。
好きなお友達を独り占めする
誰しも一緒に遊びたいなと思うお友達はいるもの。しかし、娘は仲の良いお友達が他の子から遊ぼうと誘われていると、「今私が○○ちゃんと遊んでるから、ダメ!」と言って、娘の好きなお友達を独り占めしようとします。
筆者は、みんなで遊べば楽しい事が二倍にも三倍にも増えるのに…と思いますが、娘は特定の子とだけ遊びたがり、後から来たお友達を仲間に入れません。
お気に入りのおもちゃを自分のものにする
娘は、ピンク色や可愛いものが大好きで保育園にあるピンク色のブロックや可愛いおもちゃで真っ先に遊ぶようです。他の子が娘のお気に入りの遊具を触ろうとすると「ダメ!今使っているから」と言って貸してあげることができません。
この先、娘が自分の気持ちばかり優先して遊び続けることで、お友達から嫌われてしまうのではないかと筆者は心配をしています。
強い口調や言葉で話す
3歳~4歳の子どもは、時に自分のやりたい気持ちが優先して強い口調になってしまうのは分かるものの、お友達が傷つくような言葉を選んで言っている場合は、親として気になります。
今のところ、「ダメ!」「今私が使ってる!」といったように、自分の主張や気持ちを強い口調で話しています。これから先、年少や年長、一年生となり、相手を傷つけるような言葉に発展しないように、気を付けていかなければと思っているところです。
お友達との関わり方、親はどう対処すべき?

画像:AC
年少さんくらいの幼児は、お友達とのトラブルを体験して、相手を思いやる気持ちやお友達との関わり方を学んでいくものです。とはいえ、3~4歳の子ども同士でお友達トラブルを解決できる年齢ではないため、親が関わる必要があります。
ここでは、娘にお友達とのトラブルが起きた際に、筆者が対処してみて良かったと思う関わり方をご紹介します。
親から子どもへの声がけ
娘がお友達との関わり方で気になることがあった時に、筆者から娘に声がけをしてみて、お友達との関わり方が上手になったなと成長する様子が見れた、声がけ方法をご紹介します。
- 我慢をして譲ることを教える
- 娘とお友達の個性を尊重する
- 保育園にある遊具は共有のものと伝える
- お友達の立場に立って考える力を育む
我慢をして譲ることを覚える
保育園や児童館、公園には我が子がお気に入りの遊具がありますよね。赤ちゃんの頃は、小さな子がお気に入りのおもちゃで遊ぼうとすると、お姉さんやお兄さんは先に遊具を使っていても譲ってくれた経験もあるはずです。
自分の気持ちを我慢をして譲ることを覚えるには、まずやさしい心を育む必要があります。やさしい心を育むには、やさしさに触れる経験が必要です。
普段から娘にやさしく接してくれる年上のお子さんや、大人がいたら、筆者は娘に「やさしくしてもらえてうれしいね」と伝えています。
娘とお友達の個性を尊重する
我が家の娘は、平均よりかなり背が高くて力もあり、活発に動くのが大好きです。そのため遊具の高い位置まで一人で登ってお友達にも「同じところまで登ってきて」と言うものの、お友達は怖くて登れません。
筆者が娘に「お友達と一緒に遊べる高さで遊ぼうね」と言っても、娘は、お友達が来てくれないし、ママは嫌なことを言ってくる」となってしまいます。
無理して遊びを合わせることをせず娘ができていることは褒め、お友達は登りたくない気持ちなんだってと、双方の個性と気持ちを尊重するようにしています。すると、娘は自分の気持ちが満たされ、お友達の気持ちも理解しようとしてくれるのです。
保育園にある遊具は共有のものと伝える
年少さんはまだまだ、保育園や公園にある遊具を独り占めしたくなる年齢でもあると思います。そして、そろそろ共有の遊具であることも理解できるはず。
筆者は、公園にある「公園利用のルールの看板」を見ながら、遊具は譲り合って使うんだよ、公園にゴミは捨てないんだよなどと教えています。
「公園利用のルールの看板」は、イラストで描いてあるものもあって子どもにも分かりやすいため、娘もイラストを見ながらなら楽しく、公共の公園を使うルールに興味を持って覚えられる様子です。
お友達の気持ちを考える力を育む
1歳~2歳頃に、児童館や公園で、お友達とおもちゃの取り合いになる時期がありますよね。赤ちゃんの頃はイヤイヤ期が起因していたり、周りが見えず相手の子どものことより自分を優先するものです。
その一方で、3歳~4歳頃になると娘の場合、お友達が一緒に遊びたがっている、おもちゃを使いたがっているといったようにお友達の気持ちは分かるようになってきます。そのため、筆者が娘に「○○ちゃんもこのおもちゃで遊びたいと思っているんだよ」と穏やかな口調で伝えると娘も「分かった。」と言ってくれます。
我が子ならお友達の立場に立って考える力を育むことができると信じるのがポイントです。すると、お友達の気持ちに寄り添った行動ができます。
親ができること
娘の気が強いのは、筆者の普段の言動が影響していることもあるのかなと思う時があります。そこで、娘のお友達トラブルに影響しそうで、筆者が改善できることを考えてみました。実際に親の行動を変えてみて、娘に伝わったと思うことをご紹介します。
- 親が乱暴な言葉や否定的な言葉を使わない
- 親が楽しい気持ちになるような言葉を使う
- 我が子の個性に合う習い事をはじめてみる
- ママや家が安心できる場所であることを伝える
親が乱暴な言葉や否定的な言葉を使わない
何気なく普段親が使用している言葉を、我が子がマネして喋っている姿を見たことのあるママも少なくないはず。年少さん位の年齢だと、言葉の本質的な意味も分からずに、親の言葉をマネしてお友達に言ってしまうことがあります。
普段から親がキレイな言葉で娘に接することで、乱暴な言葉や否定的な言葉が出ないようにしましょう。
楽しい気持ちになるような言葉を使う
小学校一年生の息子が年少さんだった時を思い返すと、周りを楽しくするような言葉や、やさしい言葉を使っているママの子どもが、お友達が傷つくような言葉を頻繁に言ってしまうのを見たことがありません。
周りから好かれるような言葉を、我が子が自然と使えるようになるには、先ずは親が素敵な言葉を使う必要があるのだと思います。我が子と一緒に楽しめる話題を探してみましょう。
個性に合う習い事をはじめてみる
保育園の集団生活では、自分の思い通りにいかないこともあり、子どもながらに疲れを感じていると思います。また、やりたい遊びができずストレスに感じる場合もあるでしょう。
小学校一年生の息子は、身体を動かす遊びが大好きだったため、保育園での鬼ごっこやドッジボールだけでは満足できませんでした。そのため水泳と野球をはじめたところ休日の習い事を楽しみに、保育園生活を過ごすことができました。
個性を発揮できる習い事をはじめ、その子の良さを伸ばすことができることで、お友達の良いところにも気づき、お友達を尊敬する心が育まれるのだと思いました。
ママの側や家が安心できる場所であることを伝える
朝から夕方まで保育園にいるのは、大人が会社に行くようにストレスを感じたり、疲れたりするものです。ママの側や家が安心できる居場所であることで、園生活も頑張れるはず。
我が家の娘は家の中ではプリンセスになりきって大きな声で歌ってダンスするのが好きで、好きなように動いてリフレッシュしています。
お友達と上手に関わるためにも、子どもながらに息抜きは必要です。我が子が家の中で好きな遊びを楽しんでいる時は、居心地の良く安心できる家を作ってあげるようにしましょう。
まとめ
年少になると、お友達と関わりながら遊ぶ機会がでてきます。楽しく遊べる時もありますが、上手く関われないこともたくさんあります。
お友達を尊敬する気持ち、相手の立場に立って考える必要性、時には我慢することの大切さ、お友達にやさしく接することなど、我が子の性格に合わせたサポートをしてあげましょう。周りのお友達への配慮を覚えることも必要ですが、もちろん我が子の気持ちを大切にすることが大事。
お友達と上手に関わって楽しい保育園生活を過ごせるよう、今回ご紹介した対処法を参考にしてみてください。
【あわせて読みたい】
・【保育園・幼稚園】子どもが友達から嫌いと言われた!意地悪なお友達の対処法をご紹介
・【保育園】ママ友と仲良くなれない人の行動や特徴とは?ママ友ゼロで寂しいと感じたときの対策
・保育園の後、公園へ寄り道して帰りたがらない!降園後に3年半、公園で遊んでみて分かったこと
・保育園の洗礼はいつまで続く?復帰早々「仕事に行けない…」1歳の娘が1年間に休んだ頻度と理由、対策をご紹介!