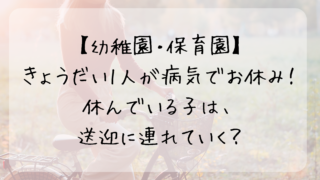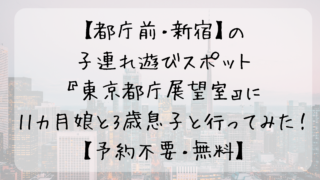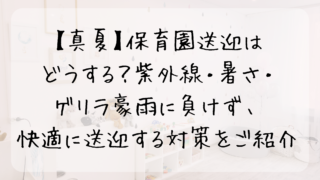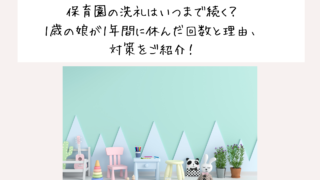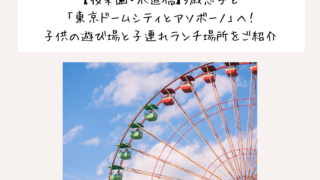近年、共働き世帯が増加傾向になりつつありますね。一方で、ママの家事と育児の負担はあまり減らない傾向にあり、共働きがしんどい…と感じているママも多いはず。
今回は、共働きママが、「家事・育児と仕事の両立がしんどい…」と感じる理由とママの負担を楽にして毎日を楽しく過ごす方法をご紹介します。
共働きママが子育てと家事の両立がしんどいと感じる理由

共働きのママの中では、「仕事と家事・育児の両立がしんどい」と感じたことのある方が少なくないはず。
その背景に、共働きママは、パパより家事・育児の負担の割合が大きいことがあげられるのではないでしょうか。仕事が終わった後にご飯を作ったり、洗濯や掃除をしたりするのは本当に大変ですよね。
さらに、働いている中で感じるママ自身の将来のキャリアに対する不安もある思います。
この記事を書いている筆者も共働きの保育園ママで、仕事・家事・育児の両立がしんどいと感じたこととが何度もあります。
そこで今回は、筆者自身が共働きがキツイと感じる理由、ママ友の話の中から共働きがしんどいと感じる理由をまとめてご紹介します。
当てはまる項目があるかないか確認し、しんどい状況を変える方法を見つけましょう。
ママに偏りがち?!共働きの家事がしんどい

ママが時短=無意識に平日家事・育児はママ担当に
ママが時短勤務をしていると、育休時のそのままの流れで家事・育児のほとんどがママ担当から変わらずの状態になっていることもあるのはないでしょうか。
職場復帰した後の時短勤務とはいえ、ママ1人が家事と育児をこなすのは、負担が大きくしんどいと感じると思います。
このままだと、お子さんが大きくなったらフルタイム勤務するようになったらますますママの負担は増えるでしょう。
保育園の手厚いサポートや時短勤務をしている期間中に、ママとパパの家事負担の割合を見直しておけると良いでしょう。
名もなき家事に気付くのはママだけ
ゴミをまとめる、食べこぼしの床を拭く、洗剤を補充する等、名もなき家事に気付いて対応するのはママだけと感じた時、ストレスが限界を迎えます。
パパに言ったところで、嫌な顔をされたり、言い返されたり喧嘩の原因になり、余計にイライラすることにもなりかねません。
名もなき家事もリスト化し、役割分担することをオススメします。
仕事後、保育園に迎えに行った後のご飯作りがしんどい

仕事が終わって疲れている中、夕ご飯の準備をするのは一苦労です。お子さんが小さなうちは、離乳食と幼児食、大人用の食事を作らなければならないのも大変です。お子さんが小さなうちは、子どもの面倒を見ながら料理をするので、思うようにすすまず疲れが倍以上に感じることも。
我が家では、朝お肉に味を垂れの入った袋に入れて、夕飯は焼くだけで大丈夫なようにしたり、スーパーでカットと煮込みが終わっている野菜を買ってカレーやシチューを作るようにしています。
また、食事作り担当が、食材の買い出しをしないと、食材や食費のやりくりが出来ないものしんどいです。
食事作りを担当しているママは、休日にスーパーで食材を買い出しに行ったり、仕事の休憩中にネットスーパーを利用したりと常に食事作りのことを考えています。
子どもの食事作りとなると、栄養面も考える必要があったり、大人の食事と別の食事を作る必要があったりするので、食事作りが大変なのです。
共働きの子育てとの両立がきつい

夜泣きの対応はママ一択
赤ちゃんが産まれてから、夜のミルクやオムツ交換はママの仕事になっているご家が多いのではないでしょうか。
この流れで、ママが仕事に復帰をしても子どもの夜泣き対応はママ一択になっているのです。
お子さんが小さな時から、パパも夜泣き対応をしないと、お子さんが成長した後になっても夜泣き対応はママでないとダメな状態になりかねません。
寝不足で仕事をするのは体力的にも精神的にもしんどいことなので、こうならないように職場復帰を考えているママはお子さんが小さなうちから、パパにも夜泣き対応をしてもらいましょう。
予防接種、健康診断はママが管理
お子さんが3歳になる頃まで間の期間はあるものの、予防接種と健康診断が続きます。
これも、赤ちゃんが産まれた時の流れなのか、予防接種と健康診断は自然とママ任せになっているご家庭も多いでしょう。
時短勤務をしていることに加えて、予防接種、健康診断で定期的に仕事を休むとなると、共働きママは育児の負担が大きいと感じてしんどいと感じる原因になります。
ママとパパでお互いの仕事の状況を見て、行ける方が行くようにしましょう。
④保育園からの呼び出し対応や看病はママの役割
お子さんが保育園や学校で体調を崩した時、呼び出しの電話がかかってくるのは何故かいつもママが先。ママ自身も、自然の流れで呼び出し対応はママだと思っている場合が多く、そのことについて悩みます。
ママが必ず行くのではなく、仕事の都合がつきやすい方がお迎えに行くようにしましょう。
共働きをしてみたものの、仕事がきつい

将来に対する不安から負担を感じる
共働きママが家事・育児の負担が大きいと感じる理由に、将来の仕事に対する不安があります。
ママの中には、現在の疲れより、将来を想像した時の方が不安を感じて疲れるというママもいるでしょう。この記事を書いている筆者も感じている、将来の不安とはどういうことなのか?お伝えしたいと思います。
マミートラックから抜け出せない
育休が明け、職場復帰したての頃は、育児のための時短勤務制度は有難いと思うものです。しかし、職場復帰にも慣れた頃「このままマミートラックから抜け出せないのでは」と感じると、時短勤務への配慮は嬉しい一方で不安になることがあります。

働きたい気持ちがあるのに、働く時間も無く、成果を上げる場所も無いとなってくると、全てが中途半端に感じて家事・育児が負担に感じてしまうのは自然なことです。
将来のキャリアに対する不安
お子さんが産まれてから我が子が社会人として自立をするまで、約20年あります。
その間、乳幼児はお子さんに手がかかる、小学校は帰って来るのが早い、中学生になって一人でお留守番出来るようになっても夕飯までには帰らねばならない、高校生は受験を控えているので親のサポートが必要、などなど。
出産してからも、育児と家事は約20年続きます。子育てにはお金がかかるものです。育児・家事を約20年しながら、仕事もすると思うと、気持ちが持たないと感じるママも少なくないはずです。
共働きママの家事・育児の負担を解消る対処法5選

- 家事負担の割合をパパと話合う
- 予防接種、健康診断にはパパが行く
- 保育園の呼び出し対応、看病はパパの日も作る
- パパにも夜泣き対応に慣れてもらう
- 時短便利グッズとリラックスグッズに頼る
①家事負担割合をパパと話合う
共働きママが、家事負担を多いと感じている場合は、一度パパと話合ってみましょう。
食べた食器を洗う、お風呂を洗う、食べこぼしの床を拭くことは、パパが仕事が終わって帰ってきてからでも問題ないことです。
とはいえ、家事が苦手なパパもいると思います。食器を洗ってもシンクを拭かない、コンロは油だらけ等、パパの家事の仕上がりに不満を感じるママもいるでしょう。
パパも仕事から帰ってきて疲れていると思うので、最低限の家事をやってもらうようにし、休日や出来る時に、気になっている家事をするようにした方がママも気が楽です。

お互いが無理なく出来るように家事分担を考えましょう。
②予防接種、健康診断はパパと分担する
予防接種と健康診断にママが行くというご家庭も多いですよね。筆者は、集団の健康診会場にパパ1人で来ているご家庭を見かけたことがないかもしれません。
パパにも予防接種と健康診断へ子どもを連れて行って欲しいものですが、子どもの予防接種と健康診断は、継続的に行われるものなので、毎回ママとパパで交代していると、いつ受けたら良いのか分からなくなってしまう場合があります。
予防接種はママ、健康診断はパパのように役割分担をしてあげると進めやすいですよ。
③保育園の呼び出し対応、看病はパパの日も作る
共働きママが時短勤務をしていた場合、元々時短勤務で働いているからこそ休んだら仕事が回らない場合もあるでしょう。
お子さんが小さなうちは、1ヶ月に何回も保育園をお休みすることもめずらしくありません。月に何度も看病で、仕事を休む必要がある場合は、交代で休めないか相談しましょう。

子どもが3・4歳になれば、病気で休む回数も減ってきます。子どもを1歳から保育園に預けたとしたら、病気で保育園を休みがちなのは、始めの2・3年間です。
共働きママにとっては、体力的にも精神的にも大変な時期なので、ママとパパで協力して乗り切ることが大切です。
ママ1人で頑張るのには限界がある時期なので、夫婦で力を合わせて頑張ることも検討しましょう。
④パパにも夜泣き対応に慣れてもらう
1歳を過ぎても、夜にまとまって寝てくれないお子さんもいますよね。
我が家の長男も2歳頃まで夜に何回も起きていました。1歳10ヶ月の娘もあやせばすぐに再度寝てくれますが、未だに5回位夜中に起きます。
睡眠時間が細切れになると寝不足で疲れてしまい、仕事どころではないでしょう。
夜泣きの対応は慣れている大人がしないと、子どもが余計に泣いて寝れなくなってしまうと思います。
子どもが小さな時から、共働きでママが仕事に復帰することを見据えて、パパも夜泣き対応に慣れておくことをおすすめします。
⑤時短便利グッズとリラックスグッズに頼る
共働きママの負担を減らすためには、時短便利グッズに頼るのも必要です。2児のママである筆者が、より実用的な時短便利グッズをご紹介します。
料理の負担を軽減|みじん切りチョッパー
子どもが小さなうちは、野菜を細かく刻む必要がありますよね。包丁で切っても、なかなか細かくならないし、時間がかかります。ざっくりと切った野菜をみじん切りチョッパーに入れて、5~10回位、紐を引っ張れば、細かく野菜が切れます。
我が家は、子どもが大好きな餃子の具作りに良くつかっています。玉ねぎ・キャベツが数秒で細かくなります。簡単に手作り餃子が出来ます!
掃除の負担を軽減|無印壁掛けフック
床に衣類や帽子が落ちていると気になりますよね。無印の壁掛けフックは木材の温かみをしっかりと感じることが出来るのがおすすめのポイントです。
無印には3連のフックもありますが、筆者はスッキリと見えるのを好んで1個のフックを選んでいます。
健康を意識したハーブティーで元気に|エキナセアハーブティー
エキナセアは古来からあるハーブで、不調の緩和を目指します。
筆者は、「身体が不調に傾きそうだな…」と思った時に飲んでいます。飲むと、身体がポカポカして心地よいですよ。
まとめ
共働きママが、仕事・家事・育児の両立が大変と感じる理由と、対処法5選をご紹介しました。
共働きママは、自分の将来のキャリアを考えた時やママに家事と育児の負担が偏っている時に、大変だと感じることが多いものです。
共働きの難しさを感じたら、今回ご紹介した対処法を参考にしてみて下さいね。